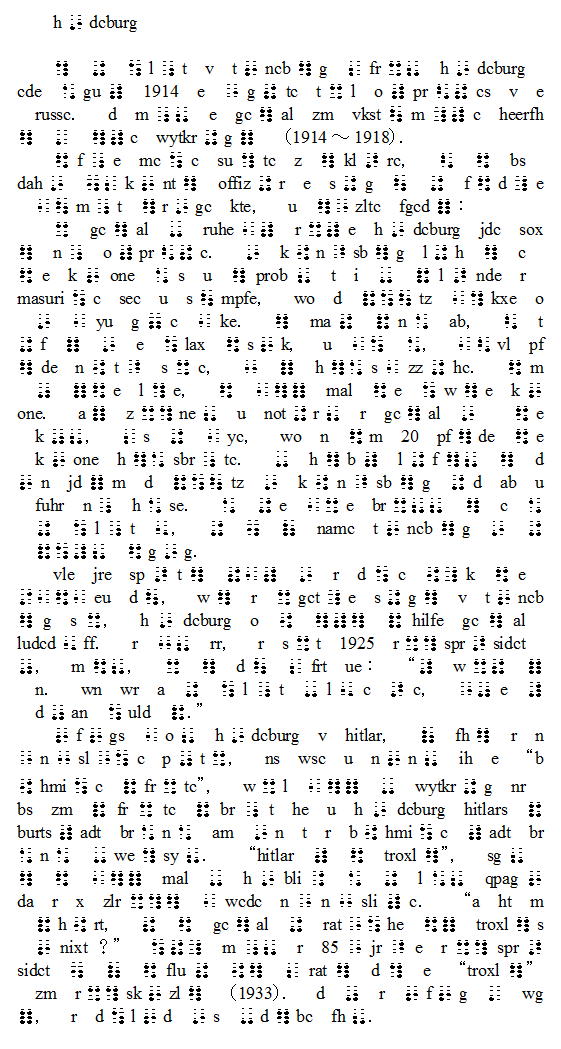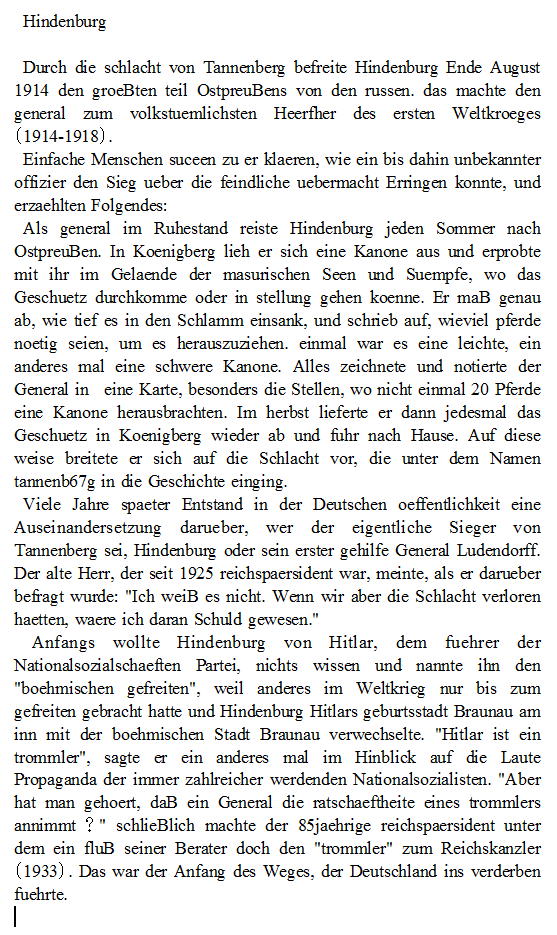| Uka78 トップページへ | |||||||
| 漢点字の散歩(17) 岡田 健嗣 |
|||||||
|
|||||||
5 点 字 2. ドイツ語点字(5) まとめ ここまでドイツ語点字について述べて来たが、本稿が依拠して来たのは、"Leitfaden der Deutschen Blindenvollschrift"及び"Kurtschrift"という2つのテキストである。この2冊の書物に加えて、"Lese- und Uebungsbuch der Deutschen Blindenkurzschrift"という点字版の読みの練習帳がある。これはドイツ語点字の初歩から二マス略字までをその段階を追って登場させて、その触読と使用の実地を習得させようというものである。点字の符号と使い方のルールを学んだとしても、実際にどのように使われるかは、使われている文章を読まなければ分からないからである。 この書物は、フランク王国の成立から20世紀までのドイツの歴史を彩った、その時代の1人の人物に焦点を当てて記述されている。1人1人の人物に代表させながら、その時代を紹介する方式の読み物である。分量はごく短いものだが、私のようにドイツの歴史といえば、高校の世界史で習った程度の知識しかない者にとっては、読み通すだけで、案外博識になれるかもしれないものである。 その中から、「ヒンデンブルク」の項を文末に引用して見たい。 これは点字書から引用するもので、アルファベットと点字符号の交じったものが、点字の文をそのまま写したものである。もう1つは、点字の略字を解放して、アルファベットに置き換えたものである。 ドイツ語点字では、大文字と小文字の区別をしない。ドイツ語では通常、行頭や"Satzpunkt"(ピリオド)の後の文字、そして名詞の頭の文字を大文字で表すことになっている。"Sie"は「貴方」、"sie"は「彼女」と読み分けるのも、動詞の格変化を見なくとも、大文字か小文字かの判別でできるようになっている。しかし点字では、大文字と小文字の区別はしない。(英語でも同様である。) そこで略字の解放文で、大文字にすべき文字を大文字にしていないという、基本的なミスを犯している懼れがある。それは私の力量不足によるのであって、ドイツ語点字の原文は、点字符号とアルファベットの交じった文のように、大文字と小文字の区別はしないのである。 例示する文にご紹介されているヒンデンブルクは、第一次大戦の英雄で、帝政崩壊後の共和国の2代目の大統領を務めた人物である。ヒトラーを首相に任命して、ワイマール共和国の崩壊を早めた人としても有名で、ここでは「歴史的汚点」と評価されている。 私は現在のフランス・ドイツの礎を築いたピピンやカール大帝の項の文章を引用したかったのだが、残念ながらそこには略字が使用されていないことと、また他の項で取り上げられている人物は私には馴染みが薄いことから、ヒンデンブルクの項を選択することにしたのである。 この2つの文を一見したところでは、分量的な相違は見出せないかもしれない。しかしそれは、アルファベットは半角で、点字符号は全角で表記されているからに他ならない。これを点字に置き換えて見れば、全てが同じ大きさの文字になって、略字交じりの方が、3割ほど少ないことが分かる。3割分量が少ないということは、触読する指の守備範囲が、単純計算で約3割増すことを意味する。視野が3割広がることを意味する。 ところで"Kurzschrift"の語は通常、「速記法」と訳される。確かにドイツ語点字を書く時にも、この略字を使うことで、より効率的に行えるはずである。その意味では「速記法」と受け止めてもよいのかもしれない。しかしこの開発の本来の目的は、触読を如何にスムーズに行うかという点に置かれていた。読み辛かった子音の並びや重母音、そして頻出する単語などを1つあるいは2つのマスで表すこと、そして自在な語の結合に耐えうる法則の構築は、如何に読むかという1点を目指したのである。そこで本稿では、"Kurzschrift"の訳語として、「略字法」を採用することにした。 このように英語にせよドイツ語にせよ、欧米の言語に位置づけられる点字は正しく文字であって、それぞれの言語の、息の長い研究と試行錯誤の結果として、1つの体系が構築されている。振り返って我が国の視覚障害者教育と触読文字の開発は、欧米の制度を輸入しただけの、極めて上辺だけの浅薄なものに留まっている。日本語を表記する文字の開発を忌避し、視覚障害者の漢字教育が無視されるというのが、現在実施されている「教育」なのである。そんな中で日本語の表記の研究に踏み込んだのが、唯一川上泰一先生だったのである。 なお引用のアルファベット文では、"sz"を"B"で、ウムラウトを"e"を後置することで表した。 |
|||||||
|
|||||||
| 前号へ | トップページへ | 次号へ | |||||